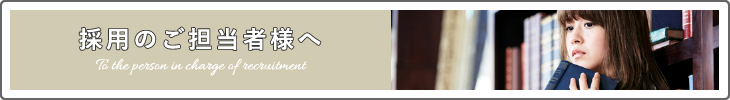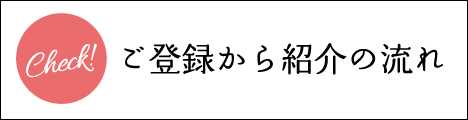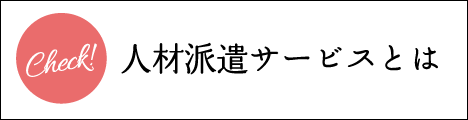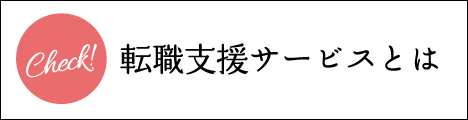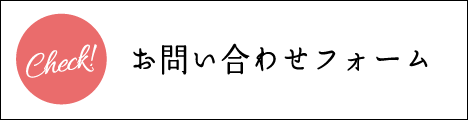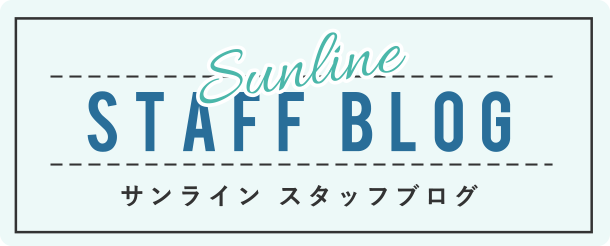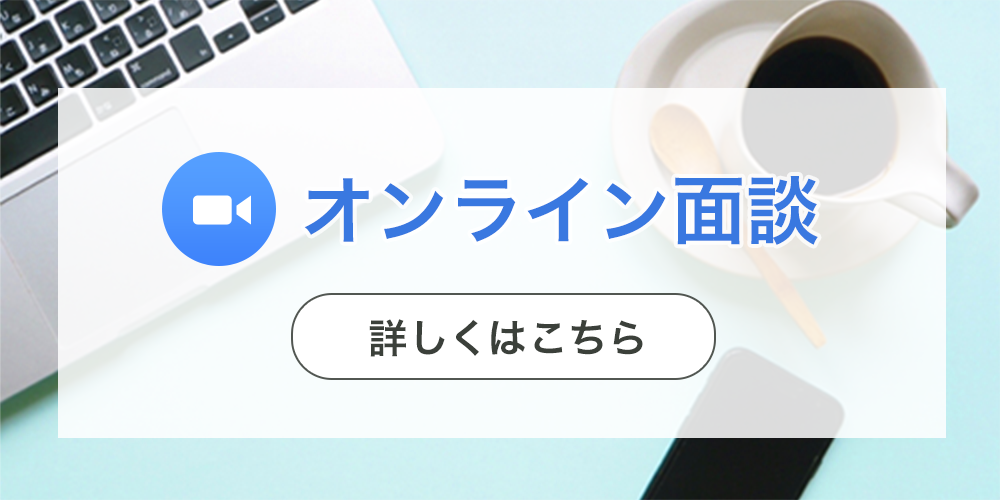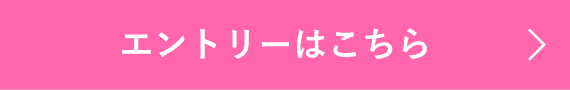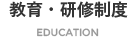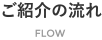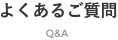スタッフブログ
STAFF BLOG
入浴介助時感染症利用者の順番?入浴時の流れ?手袋などの入用?
2021.12.24

施設の利用者さんたちや自宅介護において
入浴で大変な思いをされたり悩まれたりする方も多いかと思います。
特に施設介護においては、
感染症を持っている人の入浴の順番に気を付けようと思う方が多いでしょう。
まず入浴介助では下記汚染による感染が考えられると言われています。
①浴槽の汚染
②湯の汚染
③入浴器具用具の汚染
④介助者による交叉感染
まずお答えできる事としては、
梅毒、C型肝炎、B型肝炎、MRSA・緑膿菌 など
通常では入浴による感染の可能性は無いと言われていて
お風呂に入る順番を気にする必要はありません!
また上記感染症の主な感染経路としては…
◆梅毒:「性行為での感染・血液感染」
◆C型肝炎・B型肝炎:「血液を介して感染」
※通常の状態では感染はしません。
しかし感染経路の中でも、
『肝炎の利用者に使用した「注射針」が看護師に刺さり感染した』
という事例があるので、注射針の処理には注意して下さい。
◆MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌):「接触感染」
①直接患者に接触すること
②介護用具や環境表面(間接的に感染する事もあります)
これはどの程度の菌がどこから出ているかによりますが、
入浴により他の利用者さんへ感染する可能性は少ないと考えられています( ..)φ

一般的に、入浴後は風呂用の洗浄剤を用いて洗い流した後、
高温のお湯をかければ、特に消毒の必要はありません。
「銭湯や温泉で感染した」という事例もないので
入浴では簡単に感染しないと考えても問題ないでしょう。
・・・一方で、
褥瘡(じょくそう ※)がある利用者さんの場合、
MRSAの対応には順番を検討する必要があるともされています( ..)φ
(※患者が長期にわたり同じ体勢で寝たきり等になった場合、
体とベッドとの接触局所で血行が不全となって、周辺組織に壊死を起こすものと定義されています)
順番を検討する場合は、
「利用者の傷の有無」が肝となります。
極論、利用者さんと介助者の皮膚に傷がなければ、
梅毒、C型肝炎、B型肝炎、MRSA、緑膿菌などの菌は
お互いの体内に侵入する事はできません。
しかし、両者に皮膚に傷があった場合には、
感染する確率があるため注意が必要になります( ..)φ
かなりの低確率らしいですが、ゼロではないとされているそうなので、
「とにかく傷には気をつけろ」デスね!
介助者に傷が無かったとしても、
感染症に感染している利用者の傷に直接触れる場合には手袋を着用する必要があります。
(どちらにも傷が無い場合には、手袋を使用する必要が特に無いみたいです)

傷がある場合には、入浴を最後にする他にもシャワー浴など
臨機応変な対応が必要になります。
また自分を守る為の感染症対策には、
いかに「手荒れ」をさせないかが重要となってきます!
保湿する事で乾燥等の肌荒れを抑える事ができますので、
入浴や手洗い後など水に触った後はこまめに保湿できると◎ですね。
(仕事柄難しいかとは思いますが…最大限の努力を!)

自分の手に傷がある場合は、「手袋をつける」などの感染対策をしてください。
正しい知識を身につけて、正しい対応を心がける、
そしてピンポイントの対応を行うのが、プロです!
※「入浴時における感染対策」についてのブログも書いていますので、ぜひ読んでみて下さい!
⇩⇩画像クリック⇩⇩
感染症の他にも、入浴介助にはたくさん注意する事がありますが、
その中でも最近注目されてきたのが、「ヒートショック」と呼ばれるものです。
暖かい場所から急に寒い場所へ移動した時に、
血圧が大きく変動することで、失神や心筋梗塞、脳梗塞などを起こします。
場合によっては死亡事故へと繋がる可能性が出てくる危険な症状です。
このヒートショックを防ぐには、
浴室と脱衣所の温度差を少なくすることが大切で、
特に冬場の温度差には、注意が必要となります!
入浴前にはシャワーなどを使用し、
「浴室を温めておく」などの対策をしておきましょう。
今回は、感染症の入浴順番についてブログを書きましたが、
身体を洗う順番についてもブログを書いていますので、
もしよかったらこちらも読んでみてください(*^^*)
※「入浴介助時の体を洗う順番」(青字クリック)